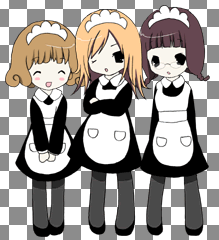
天気のいい日曜日のディズニーランドに行くのは、行列しにいくようなものだ。それでちょうどよかった。話すことがたくさんあった。日本政府の動き、千葉の政治的な雰囲気、財団の内情。
「警護部は増員されたけど、フルタイムのメイドはいま4人しかいない。バイトを入れてるけど、これが役立たずでねえ。お客の前には出せない連中だし」
私のいたころから比べると、王位継承者の数、つまり財団の財源が三分の一以下に減った。外交上の応接をすることが少なくなった現在、メイドの頭数が削られるのはしかたない。
「バイトを入れて、安全上は問題ないんですか?」
「全員が職員寮だから、素行はつかめてると思う。情報は、ある程度はしょうがないね。陛下がどんなかたか、もうあらかた知れ渡ってるから、いまさら神経質になっても」
あとから考えれば、パートタイムなのに職員寮に入っている、というところで疑問に思うべきだった。けれどそのときはなにも思わず、
「陛下の人気はいま上昇中のようですが」
と、次に行ってしまった。
昼過ぎに、
「あのレストラン、まだあったんだ」
と美園は園内のレストランを指さした。
「あれがなにか?」
「覚えてない? 前に来たときにあそこで食べたよ」
それで思い出した。
まだお昼どきということもあって、ここも行列だった。とはいえ、今日のような日は、どこに行くにも行列だ。かなり並んでから、やっと店内に入る。
「さて。
前置きは、これくらいでいいかな。
ひさちゃんと別れたでしょう。どうして?」
「よくご存じですね」
「車の名義を移したでしょう。ロシアでも自動車の登録名義は公示されてるの――ってのは建前だけど。
でもって、ひさちゃんを連れずに帰国するっていうからさ、こりゃ別れたな、って。そしたら帰国して一番最初に私に連絡つけてくれた。嬉しかったな」
今度は聞き逃さなかった。
「どうして一番最初だとわかりました?」
「成田空港に監視カメラがいくつあるか知ってる? 携帯の通信もモニターしてるし」
最近では監視カメラ映像の分析能力が向上していて、何万人もの人間を同時にリアルタイムで追跡できるという。
「護衛官の職務と関係のない情報をずいぶんお持ちですね。財団の機密保持能力が心配になってきますが」
「ああこれ財団抜きで内務省から直接。私、保安局員だったの。護衛官と兼任できないから今は違うけどね、形式上」
内務省保安局――いわゆる諜報機関だ。会議などで何度か局員を見たことがある。それぞれ別人だったのに、同一人物のように思えて仕方なかった。全員が全員、雰囲気がそっくりなのだ。
「……は?」
いったいなんの冗談かと思ったけれど、美園が握っている情報は本物だ。私に手を出したり、浮気がバレて離婚したり、でたらめなことばかりしているこの美園が、あの無個性な保安局員?
「ついでにいうと、歳も3つサバ読んでる。これから一生サバ読んで通すから、いやあ得した。
陛下は保安局のやり口にお詳しいからね。お側仕えのメイドを中学生で揃えろ、なんて言ったのも、私みたいなのを入れたくなかったんでしょう。でもこっちも仕事だから、備えはあったわけ。つまり私。
国王財団に新卒で入れなんて、退職勧告みたいなもんだけどさ。辞めないで粘ってたら、陛下がご即位なさって、これだもん。人生っておいしいわ」
退職勧告同然の扱いを受けたということは、美園は保安局でもなにかやらかしたのだろう。
「……陛下はご存じですか?」
「たぶんね。でもまさか、『バレてますか?』なんてお尋ねできないでしょう。
でも、ひかるにはバラしちゃった。なんでかっていえば――もう護衛官をやめるから」
予想してはいたことだった。『護衛官も千葉国王に見切りをつけた』という報道が、かつて緋沙子のことを初めて報じたのと同じ経路から出てきていた。私は念を押した。
「週刊××の木村記者は、いまでも財団の?」
「それは守秘義務。
でも、ちゃんと届くもんだね。特定個人を狙うのって、あんまりアテにしてなかったけど」
「あれは私宛てに?」
美園はうなずいて、
「ひかるをおびきよせるためにね。……実はね、今このお店、ひかる以外はみんな保安局員」
私は振り向いて店内を見回した。とたんに、美園は大笑いした。からかわれたのだ。
「こんな手間かけるわけないでしょう。ひかるに用があるなら官舎の前で押さえてるって」
思わず子供のようにむきになって私は、
「取調べでは私が口を開かないかもしれません」
「ふーん? ひかるは今日なにかしゃべったっけ? ひさちゃんと別れたことくらいか。そんな大切なことなんだ、ふーん。そりゃそうだよね?」
「……本題に戻りましょう。私をおびきよせたのは、どうしてですか?」
「ひかるは、誰に会いにきたの?」
それはもちろん陛下に――そう言いかけて。
美園が嘘つきだということを思い出す。
正面きって本心を言うことが、めったにない人間だということを、思い出す。
陛下のおっしゃることが、たとえ嘘であっても本心からなのとちょうど正反対に、美園の言うことは事実でも嘘ばかりだ。言葉のはしばしから気持ちを読み取っていくしかない。
私が誰に会いにきたのか。
わかりきった質問だった。こんなわかりきったことを、こんな顔をして、訊ねるだろうか。
私が帰国して一番最初に美園に連絡したことを、嬉しかった、と言っていた。
本のページに挟まれた残り香のように密かに、昼間の星の光のように淡く、美園は期待している。
できるだけ平気そうな顔を作って、私は答えた。
「陛下です」
「会って、それから?」
「またお側に置いていただければと」
「そういうこと。ひかるをおびきよせたのは、私の求人活動。こんなときに未経験者にやらせるわけにはいかないでしょう。いまは公募はいらないから、すぐに代わってもらえるしね」
千葉の憲法は公務員の採用について募集と選考の一般公開を定めていた。
「どうして辞めるんです?」
「退職金が欲しい。判決の後だと出ないかもしれない、って脅されててさ。貯金がぜんぜんないから、これ辛いんだわ」
美園は力説してから、ちょっと早口で、
「あと、愛と正義のため」
と付け加えた。
判決期日は2週間後に迫っている。敗訴すれば、陛下は財団幹部ともども、対テロ関連法で逮捕・起訴されるだろう。
その前に、陛下だけでも逮捕・起訴をまぬがれる道を手引きしよう、という連中がいる。それも複数いる。ただしこの連中はみな、判決の前に決心することを求めている。判決後では時間的な余裕がないというが、実のところは連中はみな日本政府の回し者で、千葉国王の権威を失墜させようと企んでいる。もし陛下が、財団幹部や支持者を放り出して自分の身の安全を図れば、千葉国王というものは存在しなくなり、再分離運動も瓦解するだろう。
「今度の水曜日に、公邸にその連中を集めて、オークションみたいなことをやるんだわ。誰が一番いい条件をつけるか。そもそも、陛下がうなずくような条件を出せるかどうか。
財団だってこんなこと、やりたくてやるわけじゃないよ。あんなチンピラどもは相手にしたくない。陛下だって連中なんかに頼るわけがない。そんなことくらいはみんな知ってるけど、ま、ケジメって奴よ。なんていっても、ほかに陛下をお助けする手立てがないんだから。
ひかるをそのオークションに加えてあげる。ただし、ひかるの出す条件は、敵前逃亡じゃなくて、徹底抗戦だけどね」
そのとき私は珍しく冴えていて、勘繰ってみた。
「美園さんはそのオークションの前に辞職を発表なさるんですね。その連中からいくら貰えるんです?」
すると美園はこともなげに認めた。
「お金が欲しい? あげるよ、全部。
そのかわり――陛下を助けてあげて。
牢屋に入れられたり、外国に逃げたりしないですむようにしてあげて。この国で、自由に生きていけるようにしてあげて。
私はそんなスーパーマンじゃないから、お金をもらってトンズラこくわけよ」
その条件に、うなずくこともできず、断ることもできずに、私は外の景色に目をやった。
帰りの車中だった。運転は美園だ。ひさしぶりに研修以外で運転する、と言っていた。護衛官は私用では車の運転をしない。あと2日で辞めると決まったから、美園は運転席に座った。
車は高速道路を南に走っている。窓の外は山と田んぼばかり、もう木更津が近い。
私はふと思いついて、試しに言ってみた。
「そのお金は、美園さん自身のために使ってください」
「どうかな。悪銭身につかず、って言うじゃないの」
なぜ美園に貯金がないのか。本人の言うとおり、子供の養育費と仕事用の衣装代もかなりの負担だろう。けれど、それでも赤字にはならない。官舎の家賃はタダ同然だし、独身では車も乗れないので必要ない。
きっと美園は、工作費の一部を、自分の懐から出した。保安局には言えない支出があったのかもしれないし、そもそも工作費がもらえなかったのかもしれない。
「美園さんのことが心配になってきました」
すると美園は急にぶっきらぼうに、
「考え事したいから、ちょっと黙ってて」
と咎めるように言った。
官舎の前で車を停める。
「さっきはごめん。寄ってくでしょ?」
「メイド服に着替えないと約束していただければ」
冗談のつもりだった。けれど美園は目を丸くして、
「なに、『まんじゅうこわい』? ひかるってゲテモノ好きだったんだ。びっくりだ。ひさちゃんとか陛下とか、あんなに趣味いいのに。人間ってわかんないもんね」
どうやら美園はからかっているつもりらしかったが、意味がわからなかった。
「なにが悪趣味なのかわかりません」
「こんなババアにあんなの着せるのが悪趣味」
「いまでもよくお似合いになると思います」
当たり前のことだと思って答えたのに、
「これだよ、女ったらしがきたよ。ひかるが変なこと言うから震えちゃってるよ私」
本当に美園の手は震えていた。私は黙ってお茶が出てくるのを待つことにした。
官舎は昔となにも変わらない。間取りはもちろん、床がきしむ場所も、ドアの取っ手の形も、身体が覚えているままだ。家具は入れ替わっている。けれど、私の身体の感覚では、なにひとつ変わっていない。
「あのねえ、私にあんまり変なこと言わないでよ」
美園がアイスティーを運んできた。
「変なことを言っているつもりはないのですが」
「ここんとこ何年も陛下しか食べてなくてさ、男が足りなくて情緒不安定なんだわ。陛下の前だと収まるんだけど。一体どんなフェロモン出してるんだあの女。
ひかるみたいな女食(にょしょく)動物にはわかんないでしょう。女を食うで女食ね。いや、わかるか。陛下の匂いにがっついてたし」
「あのとき私は情緒不安定でしたか?」
「あんたは基本的に自覚ゼロなんだよ。
まあね、あんまり自覚するのに忙しいと、いろいろ重たくなってきて、自分もまわりも、たまらんわね。自覚するより大切なことなんてたくさんあるし。私にできてなくて、ひかるにできてること、たくさんある。
でも一つだけ言っとく。
陛下と親しそうな子に、ガンつけて毒舌するのはやめて。みんな恐がってた。陛下は喜んでたけど」
私はそんなことをした覚えは――心の中で反論しかけたときに、思い当たる。
初めて緋沙子に会ったとき、言っていた。『もし設楽さまが、陸子さまのことで私に嫉妬したら、そのことを私に隠さないでください』。あれは、そういうことだったのだ。
「ひかるは相変わらず顔に出るねえ。思い当たったんなら結構。
さっき、井村さんに――女中頭に電話した。ひかるのこと、話を通すためにね。もうすぐここにくる。ガンつけるんじゃないよ。陛下はあの子には手を出してない、はず。でもそいつ、陛下は私のものです、みたいな顔したがる奴なんだわ。お面が自慢の子でさ、なんで陛下に手を出してもらえないんだろうって思ってるね、あれは。まあ、ひかると緋沙子を見たら誰だって、陛下のこと面食いだと思うか」
あとから思い返せば、このとき美園は巧妙に嘘をついていた。話の流れとしては言うはずのことを、わざと言わなかった。
「昔はひかるが年下だったから、みんな譲ってあげてたけど。今度はひかるが年上だからね。お姉さんしてあげよう。
……お説教はこれくらい」
言い終えると、美園は自分のアイスティーを一気に飲み干した。運転で喉が乾いていたのだろう。私も自分のを、美園のように一気にではないけれど、おいしく飲んでゆく。
美園が席を立ったのを、私はほとんど意識しなかった。次の瞬間、私は背後から抱きしめられていた。
「私の匂いで発情なさいませ、ひかるさま」
その言葉につられて、美園の匂いを意識した私は、その言葉どおりに動かされてしまった。
「――なーんてね。感じたでしょう? ありがと。ごめんね。情緒不安定なんだわ」
けれど腕は解かず、美園は続けた。
「ひかるにお願いがあるの。
判決が出て、陛下が…… そういうことになったら、私のところに来て。
いまの財団関係者の風向きとか人間とか、ぜんぜんわかんないでしょう。誰がなにをするかわからない。
私なら、ひかるに一番いいようにしてあげられる」
その言葉の裏にあるものが、私の胸をふさぐ。家族も失い、陛下のお側からも去り、美園はひとりになろうとしている。
「お願いされるまでもありません。私はいまこうして美園さんを頼っているのに、2週間後には手のひらを返すとでもお考えですか?」
「ひかるがどうするかは、そんなに重要じゃないんだわ。お願いすることが重要。わかる?」
「わかりません」
「そりゃそうだ。ひかるだもんねえ」
私が返事に窮していると、懐かしい音がした。玄関の呼び鈴だ。女中頭がきたのだろう。
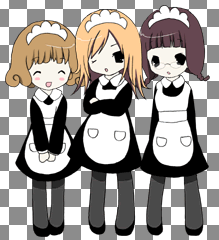
ここから完結までの物語は、書籍でお楽しみください。
メロンブックスの通販サービスで、同人誌『1492』(4200円)をお求めになれます。
メロンブックス.comにてPDFのダウンロード販売(1050円)もご利用いただけます(要PC)。