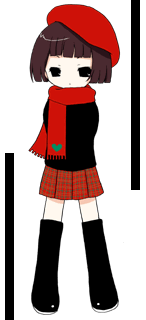
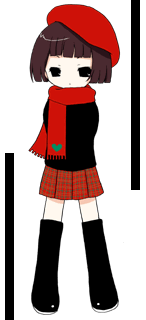
私が21歳のとき、前国王陛下がお隠れになり、国王抽選会が開かれた。
私は、父が市役所に勤めていたので、王位継承者会に入らされていた。継承者になって初めての抽選会だった。
もし国王に当選したら、どうするか。
抽選会前の継承者なら誰でもそうするように、私もそのことを考えて、決めていた。『即位する』。それが私のひそかな決心だった。
私はそのとき、どうにも行き詰まっていた。
高校を出て、まんが家のアシスタントになってから3年。まんが家としての私は、3年前から、ほとんど前進していなかった。いや、5年前からかもしれなかった。
才能がないとは思わなかった。それだけは一度も思ったことがない。いまでもマスコミが私をけなすときには、判で押したように『傲慢』と書く。運がないとも、あまり思わなかった。ただ、それを見逃しているとは思った。
『(*1)現在、米国には15世紀のフィレンツェの人口の約1000倍の人々が住んでいる。1000人のレオナルド、1000人のミケランジェロが私たちのなかにいるはずだ。DNAがすべてを支配するなら、今日私たちは毎日のように素晴らしい芸術に驚嘆しているはずではないか。現実はそうではない。レオナルドがレオナルドになるには、生まれながらの能力以上の何かが必要なのだ。1450年のフィレンツェが必要なのだ』。
こんな風にはっきり考えていたわけではないけれど、行動すべきだということは、はっきり感じていた。ただ、どうすればいいのかが、わからなかった。私のフィレンツェがどこにあるのか、見当もつかなかった。
もし国王になれば、そこがフィレンツェではないにせよ、少なくともこの行き詰まりからは逃れられる。
虫のいい願いだ。けれど、きっとたくさんの人々が、こういうことを漠然と思っている。でなければ、千葉人があんなに国王抽選会に熱中するはずがない。
国王抽選会は、朝の10時から始まり、王位を引き受ける当選者が現れるまで続く。国王財団理事長、労働党第一書記、木更津新報主筆、この三人がサイコロを振って、当選者番号を決める。当選した継承者のところにTVカメラが駆け付け、王位を引き受けるかどうかをインタビューする。イエスならその場で当選者が即位する。返答がノー、あるいは当選者が登録した住所にいなければ、またサイコロを振る。
私は、千葉人なら誰もがそうするように、国王抽選会の様子を自宅のTVで見ていた。
ひとりめ、ふたりめ、三人目と、即位を断ってゆく。みな中高年の男性だった。四人目はお年寄りの女性で、画面に映った瞬間、もしかして、と思った。前国王陛下もその前も、70歳近いお年寄りだったのだ。が、次の瞬間、きっぱりと即位を断る声が流れた。
当選者が辞退するごとに、緊張が走る。次は自分の番かもしれない――私も、そう思っていた。
五人目は若い女性だった。ノー。六人目は中年の男性。ノー。
午後3時を回り、TVのリポーターが交代した。新しいリポーターの、緊張した声が流れる、
『私の継承者番号は6465-1143です。もし私が当選したら、当選者探しがゼロ秒で済んでしまいますね。ちなみに、もし私が当選したら、ぜひ王位を引き受けさせていただきます』
三人が同時にサイコロを振り、地区番号が決まる。地区番号5426、千葉市三石区三石1~3丁目。その地区を紹介する映像とアナウンスが入り、それに続いて、ヘリからの中継映像が流れる。戦前に宅地として開発され、いまでは高級住宅街になっているとのこと。
『この地区の着陸ポイントは、三石小学校の校庭ですね。いま、安全を確認中とのことです。あっ、もうすぐ着陸するようです』
陸軍の輸送ヘリが着陸し、TV中継をするワンボックスカーが中から出てくる。
『いま、1丁目町内会の会長さんと電話がつながっています。もしもし?』
そうこうしているうちに準備が整い、個人番号(下四桁)のサイコロを振るときがきた。
4221。
中継車が走り出し、街路を縫って目的地へと向かう。新しい当選者の住所へ。
当選者の家は、お屋敷だった。緑の芝生の西洋庭園が、TVにちらっと映る。
TVを見ていて、待ち構えていたのだろう、すぐに当選者が玄関先に現れる。私と同じくらいの歳の女の子だった。室内着だろうか、高そうなカーディガンを着ている。
当選者はマイクを向けられ、あのアニメ声で、第一声を発した。
『国民の皆様、はじめまして。私は波多野陸子と申します。
ただいまより、国王を務めさせていただきます。
皆様、私とともに、誇り高い千葉を目指しましょう』
私は、なんとなく納得のいかない思いで、陛下のお顔を見つめていた。
そのときはっきりそう考えていたわけではないが、納得のいかない思いというのは、つまるところ――どうして私でないのだろう。
マスコミの報道ラッシュの第一波は、陸子陛下の珍しい生い立ちに注目したものだった。当時のTVのワイドショー流に、陛下の生い立ちをたどってみよう。
千葉市子供の家の前に捨てられていた、女の赤ん坊。生みの母親からのメッセージはなにもなかった。名前さえ。『陸子』という名前は、千葉市の福祉総務課長補佐がつけたという。
その子供の家の職員が当時、インタビューに答えている。
『見た目はいいし、頭もいいしで、それだけでも目立つ子でしたが、それ以上になんといっても、口の達者な子でした。それも、人を丸めこむんじゃなくて、敵と味方を作る子でした。
あの子が9歳かそこらのころでしたね。いじめっ子のグループが、あの子に意地悪したことがありまして。それであの子が、いじめっ子らを罵ったんです。
子供の家では、まあ、ほかの子を罵るなんてのは、よくあることです。子供ですから、本当に容赦がありませんよ。罵る相手の親兄弟や友達まで、徹底的に悪く言うんです。聞いてるとひどいもんですが、そのほうが暴力沙汰にはなりにくいんで、私らはほっときます。
でも、あの子の場合には、いけなかったですね。子供がいくら罵詈雑言を並べ立てたって、5分も続きやしないもんですが、あの子は味方を集めて盾にして、1時間くらいやっていました。私はちょっと聞いただけですが、まあ、大人だって頭にくるような、レトリックというんでしょうかね。いままでほかに聞いたことがないような、すさまじいものでしたね。
そうしたら、家の子がみんな影響されて、いじめっ子らの側とあの子の側の二手に分かれてしまって、いまにも殺し合いを始めそうな雰囲気になってしまって。いじめっ子らに謝らせて、その場を収めたんですが、あとあとまで尾を引いて、結局あの子が波多野さんに引き取られるまで、続きましたね』
このインタビューは生放送で、そのあと二度と放送されなかったが、私は覚えている。その顔と声は、トラブルメーカーへの憎しみを、はっきりと浮かべていた。
子供の家での生活のあとは、全国小学生弁論コンクール優勝のエピソードが続く。
陸子陛下は10歳のとき、まだ小学5年生でありながら、全国小学生弁論コンクールに優勝なさった。コンクールのテーマは、「正義と平和」。その弁論の様子がビデオに記録されており、何度もTVに流れたが、いつも冒頭の『耐えることは恥ではありません』という一言までしか放送されなかった。護衛官になったあとで、その理由がわかった。国王は、政治的な信念のようなものは、必要なときまで出さずにおくのだ。政治家は自分の主張によって支持を集めるが、国王はただ国王でありさえすればいい。政治的な信念は邪魔になることもある。
全国小学生弁論コンクールの優勝がきっかけで、陛下は11歳のとき波多野夫妻の子になり、子供の家から引き取られた。
波多野夫妻は当時、千葉で9番目の資産を誇る資産家だった。恵まれた環境のもと陛下は、中学と高校で優秀な成績を修められ、千大法学部に進学なさった。
陛下のご学友としてマスコミに登場した人はみな、この時代に陛下のお側にいた人だ。陛下の驚異的な記憶力と読書量、人をそらさない魅力、細やかな気配りを、申し合わせたように称えていた。
そんなとき私は、護衛官募集の広告を目にした。
表向きの動機はあった。まんがを描くうえで、実物の千葉国王を見ておくことは、いい経験になる。陸子陛下のドラマに満ちた人生にも、興味があった。陸子陛下のいわゆるアニメ声には賛否両論あったが、私は好きだった。そしてこれは文句なしに誰もが認めていた、愛らしい美貌も。
もうひとつ、誰にも言えない動機があった。
当選などありえない国王抽選会、採用などありえない(はずだった)護衛官募集。どちらでも私は、私のフィレンツェを探していた。
いま、ここは、私のフィレンツェなのだろうか。わからない。けれど私はいつのまにか、そんなことを思わないようになっていた。
*1:ポール・グレアム『ハッカーと画家』(オーム社、2005年)149ページ。
「私の服の匂いを、かいでるときみたいに。
――そう。そういう顔」
いま私には、陛下のお考えが、手に取るようにわかる。
陛下は、平石緋沙子を引き合いに出して、私が陛下にとって大切な存在であることを強調なさった。ご自分の孤独と不安を、卑下することなく主張なさった。私の言い訳がましい態度を叱って、私から言い訳を奪っておしまいになった。
私は陛下を大切に思い、陛下も私をそう思っておられる。だから私は、陛下の孤独と不安を、和らげてさしあげたい。その思いをかきたてられた矢先に、なにも気づかないふりをすることはできない。
さきほどお叱りを受けたばかりなのに、言い訳を口にすることはできない。このことが公になれば私は辞任を免れない、などと言えば言い訳になる。
そしていま、私の異常な行動を思い出させることで、陛下は私を動かそうとなさっている。
動かされるべきではない。私は陛下のお側で、護衛官としてお仕えしたい。たとえそれが、陛下のお心にぴったりと沿うことではなくても。
そう願った瞬間に、悟った。いま、ここが、私のフィレンツェなのだと。
イタリア・ルネサンスは数十年で終わり、そのあと西洋絵画はもう二度と、その高みに達することがなかった。なぜなのか。なぜ天才はどこにも行く必要がないのか。橋本美園の声がこだまする。『人は否応もなく変わっていくものです。立ち止まっていることなどできません』。
さようなら、私のフィレンツェ。
私は陛下を抱きしめた。甘い匂い。あたたかい。手が震える。
身体中が思うように動かない。陛下の唇は、すぐそこに目に見えているのに、うまくたどりつけない。闇の中ではいずりまわるようにして求め、探りあてる。
ふと自分の興奮が恐ろしくなって、顔をそらし、陛下の肩の向こうへ逃げた。
「ひかるちゃんから、キスしてくれたね」
「はい」
「ひかるちゃんて、自分からするタイプじゃないでしょ? ごめんね、無理させちゃって」
「いえ、素敵でした」
「ひかるちゃんからしてもらうのが、夢だったの。ひかるちゃんみたいな完全に受けの子が攻めるのって、すごいツボなんだ」
陛下はいつものペースをまったく崩しておられないようだった。
「お気に召していただけましたか。無上の幸いでございます」
「顔、見せて?」
私は間近に陛下と見つめあった。
「私のリップグロス、ちょっとついてる」
そうおっしゃって陛下は、私の下唇のふちを、指でなぞり、つまんで――愛撫なさった。
身体のなかで、背中の下や下腹のあたりで、衝動が高まる。けれど、なんの衝動なのか。
「私は不調法なもので、陸子さまをどのように喜ばせてさしあげたものか存じません。おかしなことをするかと思いますが、そのときにはどうぞお咎めください」
自分のジャケットのボタンに手をかけると、
「ひかるちゃん、いま脱ぐのはやばいよ? 遠野さんが戻ってくる」
「……はい」
「おあずけのできないひかるちゃんには、つらいかな? がまんできる?」
「……はい」
ふと、右手の指先が、陛下の腕に触れていることに気づく。私の指は、その腕をたどって、陛下の手にたどりつき、その指に絡みついた。
「えらいなー。我慢できないって言ったら、おりこうさんにできるように、しつけてあげたのに」
「実を申しますと、無様なところをお目にかけずにすんだもので、胸をなでおろしております」
「あーっ、かわいくなーい」
陛下は、絡まっている私の指に、爪をお立てになった。ふたたび衝動の波が押し上げる。
「ひかるちゃんは、おすまししてるときよりも、さかってるときのほうが、かわいいの。我慢してるとさらにかわいさアップ」
「はい……」
「でも我慢してるだけじゃ、だめだよね。
匂いをかぐだけなら、脱がなくてもできるよ?」
「はい」
私は、匂いをかぐのにいい位置を探した。が、
「せっかくのお心遣いですが、お顔の化粧品の匂いが気になって楽しめません」
陛下は香水のたぐいをいっさい用いられないが、化粧品には、かすかながら香りがついている。さきほどお召し替えになったばかりのブラウスも、匂いを吸い込んで弱めている。
「うーん――」
陛下は悩ましげに口をへの字になさり、それから意を決したように視線をまっすぐになさって、
「ひかるちゃん、パンツの匂いは好きじゃないんだ?」
「……考えたこともございません」
護衛官は、外出先でのお召し替えをお手伝いすることがある。私が陛下のぬくもりや残り香を楽しんだのも、そういうときだった。が、下着までお召し替えになることはなく、当然その残り香も楽しんだことがない。
が、いま想像するかぎりでは、ワンピースやブラウスの残り香を楽しむことにくらべると、それはあまりにも冒涜的に思われる。
「やっぱり引いてるー。
でもね、ひかるちゃん。私とエッチするときは、私のおまんこなめるんだよ?」
……。
…………。
………………。
「――努力いたします」
「考えたことなかったでしょ? 完全に受けだもんね、ひかるちゃんて。
でも、そういう私も、考えたことがないのでした!」
陛下は明るくお笑いになり、
「ひかるちゃんがスカートだったら、パンツをとりかえっこするんだけどなー」
「素敵なお考えですが、このあと晩餐会のためにお召し替えがございますので、遠野さんに気づかれます」
「あーあ、お仕事モードに戻っちゃった」
陛下は席を立たれて、向かい側のソファにお座りになった。
「我慢してるひかるちゃんはかわいいけど、お仕事モードのひかるちゃんは、素敵だよ」
「お褒めにあずかり光栄です」
「でも」
と、陛下は唇のそばに指をあてられて、
「人のグロスがついてると、まぬけだね」
私はあわててトイレに立った。その背後で陛下が、
「……って、私もついてるかな? やばいやばい」
晩餐会はなにごともなく終わり、私は陛下をお部屋までお送りする。
エレベーターのドアが開くと、遠野さんが待っていた。すぐに部屋まで案内してくれるものと思ったが、遠野さんは一礼すると、小さなメモを開いて、言った。
「法務の担当者からメッセージが届いております。平石緋沙子の件です。
労働法の規制のため、平石さんの就労は午後9時までとなっております。平石さんは、あくまで陸子さまのご友人として、こちらにお泊りになられます。
もう午後9時を回っておりますね。ですから明朝までは、平石さんにはお言いつけなどは一切なさらないでください。不当な労役とみなされる恐れがあります。
よろしいでしょうか?」
「はーい。
もし私がまずいことしたら、すかさずフォロー、お願いね」
「かしこまりました」
部屋にゆく。今度は警護部の担当者はいない。引き継ぎや報告などのほかは、警護部はできるだけ姿を見せずに活動する。
「ひさちゃーん?」
陛下がお呼びになると、見慣れたメイド姿の平石緋沙子が、うつむきかげんの姿勢で出てきた。
「最初に申し上げておきます。昼間のTVのあれは、財団の広報のかたの指示に従ってやったことです。まるきり嘘ではありませんが、まるきり本心でもありません」
そう言った平石緋沙子の顔は、真っ赤だった。
「いっぱいリハーサルさせられたんでしょ? わかってるって。
でも大丈夫。まるっきり嘘でも、ひさちゃんはちゃーんとかわいいよ!」
「まるきり嘘ではありません」
陛下はソファにお座りになった。
「自分のできばえ、ビデオで見た? 見てないでしょう。あれ辛いよね。でも見ないと上手にならないから、いっしょに見よう?」
その誘いに、平石緋沙子は身体をびくっと震わせて、言った。
「ここは観光地とうかがっておりますが、私はここに来てから一歩も外に出ていません。私は勤務中ではありませんので、自由に行動させていただきます。
設楽さま、もしよろしければ、散歩におつきあいくださいませんか?」
平石緋沙子は、すがるような目で私を見た。
ついさきほどの陛下のお言葉を思い出す――『うわ、ひさちゃん、すごいなー。魔性の女だ。ひかるちゃんを取られちゃうかも』。
それで、陛下のご様子をうかがう。私と目があうと、陛下は微笑まれた。
「喜んで。散歩に行く前に、平石さんは着替えたほうがいいでしょう」
「はい。少々お待ちください」
平石緋沙子は寝室に入った。
「陛下の前でも無愛想な子ですね。陛下のようなかたですと、扱いづらいのでは?」
「扱いやすい中学生なんて、こっちが気を遣っちゃうしー。
でも、どうして、ひかるちゃんを散歩に誘ったんだろうね? お友達なんだ?」
「消去法でしょう。遠野さんはまだお仕事ですし、陛下をお誘いするわけにはゆきませんし」
「ふーん?」
そのとき、平石緋沙子が私服に着替えて出てきた。半袖のブラウスに、肘まで被う手袋、ブーツにミニスカート。ベルトとポーチとブーツだけが赤く、ほかはすべて黒。手袋のほかはどれをとってもオーソドックスなもので、流行のかけらもないのに、しゃれている。
「お待たせしました。参りましょう」
田舎だけあって、夜空が暗い。星がよく見える。虫の声だけが聞こえる。
部屋を出てから一言も口をきかずに、平石緋沙子はずんずんと歩いていた。
と、立ち止まる。
「ごめんなさい。私なんかと散歩なんかさせたりして」
「私は、嫌なことは嫌だって言えるつもりだけど。
星は見えるし、静かだし、涼しいし。ご機嫌な散歩じゃないの。あとは、平石さんがご機嫌なら、申し分ないな」
「……はい」
ゆっくりとした足取りで歩きはじめる。
「平石さんに嫉妬したら、そのことを隠さない、って約束したよね。
このあいだ気がついたこと。平石さんは陛下に、『ひさちゃん』って呼ばれてるでしょう。ほかのお側仕えの人は、私以外はみんな苗字にさん付けなのに。平石さんは私とおなじに呼ばれてるんだと思って、嫉妬した。
もうひとつ。陛下が平石さんの出たTVを、ビデオでご覧になったとき、私はその場にいたの。平石さんに電話なさったときにもね。陛下が大喜びなさったから、嫉妬した。
平石さんは、最近どう?」
「設楽さまって、敬語でなくてもしゃべれるんですね」
「別人みたい? だったら、敬語にするけど」
「今のほうがいいです」
「そう」
歩みをゆるめて、うつむいて、平石緋沙子は言った。
「……陸子さまと、しっくりいかないんです」
「どうして?」
「陸子さまって、なんでも大袈裟で。私を恥ずかしがらせるのが、すごくお好きで。さっきだって、私の出たTVを一緒に見ようだなんて、おっしゃったじゃないですか。
だから私、陸子さまにいつも、憎まれ口みたいな突慳貪なことばかり言ってしまって。さっきだって、あんなこと。
陸子さまがもっと落ち着いたかたなら、私だって素直にしていられるんです」
「陛下が嫌なんだ?」
「いいえ!」
歩くスピードが急に速くなる。
「……いえ、よくわかりません」
また遅くなる。空を見上げて、
「昔は陸子さまに憧れていました。夜空の星みたいなかただと思っていました」
あんな賑やかなおかたの、いったいどこが夜空の星なのか。もしかして文通の手紙が、そういう誤解を誘うようなものだったのだろうか。
「でも今は、身近すぎて――うまく言えません。
……変な話になっちゃいますけど。
マンガなんかの話で、主人公の片腕が、別の生物やなにかに乗っ取られる、っていうのがあるでしょう。あれみたいな感じです。身体のどこかを、陸子さまに乗っ取られたみたいな気がします。
なにをしてるときでも、『陸子さまはどうおっしゃるだろう』とか、『陸子さまはどんなお顔をなさるだろう』とか、考えずにはいられません。陸子さまのお側にいないときは、ずっとそうなんです。そのうち身体のどこかが陸子さまになってしまいそうです」
平石緋沙子の言いたいことは、わかるような気がした。
「きっとそれだから、平石さんは、陛下にかわいがっていただけるんでしょうね」
「どういうことですか」
「どうって――」
わかりきったことを説明するのは難しい。私にとって陛下のご気性は、ひらがなの字の形と同じくらい、わかりきったことだった。
「――陛下はナルシストであられるから。
ただし、自分の姿を鏡に映すんじゃなくて、自分の心を他人に映すの。他人は、自分の心を映す鏡だから。他人という鏡を使って、自分の心を眺めるのが、とてもお好きなかた。
平石さんは鏡に使われてるから、片腕を乗っ取られたみたいに感じるんでしょうね」
「設楽さんはどうなんですか?」
「私は――乗っ取られるほうじゃなくて、乗っ取るほうかな。
自分が、陛下の身体の一部になってるような気がする。自分の背中から電線がのびてて、陛下につながってるんじゃないかって気がする」
「わかりました」
平石緋沙子は歩みを止めた。
「設楽さんに嫉妬するのは、もうやめます。設楽さんは、陸子さまの一部だと思うことにします。
だから私、設楽さんのことも好きです」
陛下の一部――さっきまでなら、そのとおりだったかもしれない。けれど、今は。
私はその躊躇を隠した。
「ありがとう」
「帰りましょう。陸子さまがお待ちだと思います」
平石緋沙子はきびすを返すと、足早に歩きはじめた。
私よりいくらか背の高い、平石緋沙子の後ろ姿。それを、かわいい、と思った。
姿が美しいことは、一目見たときから知っている。笑顔の鮮やかさも、心の素直さも知っている。けれど、このかわいさは、それとは質が違う。
『かわいい』。それは、そう言われた人よりも、言った人のことを表現する言葉かもしれない。私は、平石緋沙子のことをかわいいと思う、そんな人間だということだ。
「……そうだ。平石さんにもうひとつ、嫉妬。
今晩、陛下のお側で過ごせるなんて、うらやましい」
「毎日ずっと陸子さまとご一緒のほうがうらやましいです」
私は小さく笑って、
「嫉妬するのはやめるんじゃなかったの?」
「――やっぱり嫉妬します。私があさはかでした」
「今日もありがとうね、明日もよろしくね。おやすみなさい、ひかるちゃん」
「おやすみなさいませ」
平石緋沙子と一緒に陛下のお部屋に戻り、お暇を乞うと、陛下はあっさりと私を送り出してくださった。
お部屋には遠野さんはいなかった。もう自分の部屋に下がっているのだろう。陛下と平石緋沙子は、どんな夜を過ごされるのか。
ドアが閉まったあとも、立ち去りがたくて、何秒かその場を動けずにいた。もし警護部が監視しているのでなければ、もうしばらくそのままでいたかもしれない。
振り向いて、ドアを開けて、夜伽の役を私にくださるよう陛下にお願い申し上げる――そんな空想を振り切って、私はホテルの廊下を歩いていった。
翌朝のブリーフィングの終わりに、遠野さんが私に告げた。
「女中頭からの言付けです。
明日の朝9時、公邸事務所の第一会議室までご足労いただけないでしょうか。場合によっては、夕方までお引き止めするかもしれません。もし先約があれば遠慮なくお断りください――とのことです。
いますぐお返事をいただけるなら、女中頭にお伝えします」
明日は土曜日だから、警護はない。護衛官も公務員、基本的に週休二日だ。先約もない。
「行きます」
私は名刺サイズのメモを受け取った。財団職員がアポイントメントの管理に使うものだ。
陛下にくちづけたことが知られた、とは考えづらい。それに客観的には、女同士で一回キスしたくらいなら、なにもかまうことはない。
問題は、平石緋沙子のほうだろう。TVとヘリの件で、ずいぶん噂が広まったはずだ。それに昨晩、陛下はどのように夜を過ごされたのか。いままでのところ、陛下がメイドに手をつけたという話は聞いたことがないが、私に聞かせないようにしているだけかもしれない。
私の官舎から歩いて5分、職員寮と駐車場に囲まれて、目立たない小さな平屋建てが建っている。公邸事務所だ。
私は久しぶりに髪を降ろし、スカートスーツを着て家を出た。こんなときでもないと、こんな格好をする機会がない。誰かに見せたかったが、あいにく誰ともすれちがわなかった。
橋本美園も、いつものメイド服ではなく、かっちりとしたビジネススーツを着ていた。といっても彼女の場合、公邸で制服に着替えるのだから、いつもこういう姿で通勤しているのだろう。頭にヘッドドレスと髪飾りがないと面変わりして見える。
「おはようございます」
と言いながら私が会議室に一歩踏み込むと、挨拶も抜きに、
「平石さんをどうお思いですか?」
鋭い視線だった。私の言葉よりも反応が見たかったのかもしれない。
「子供です。かわいい子です」
「そうですか」
言って、橋本美園はにっこりと笑い、
「これからディズニーランドはいかがでしょう?」
と、ディズニーランドの前売りパスポートを2枚、差し出した。
私はいったん官舎に戻って、カジュアルなものに着替え、メイクにも手を加えた。
外に出ると、橋本美園はもう着替え終わって、官舎の前で私を待っていた。緑色の平凡なセダンが、橋本美園の車だった。
「あれ、眉まで変えたんだ? もしかして気合い入ってる?」
橋本美園の言葉遣いが変わったので一瞬とまどったが、カジュアルな格好であんな敬語を使うほうがおかしい。
「あまり遊びに行かないぶん、精一杯やろうと思いまして。こんなおめかしも久しぶりです。おかしくありませんか?」
「その顔だと、うちの子みたいよ。大丈夫、まとまってる。
ひかるさん、免許持ってるよね?」
「ええ。でも、公務以外では運転しません。免停にでもなったら公務に差し支えますので」
公務といっても、年に一度、実技研修でおさらいする以外はハンドルを握らない。私の運転免許は、緊急時に備えてのものだ。
「なるほどね。帰りは運転お願いしたかったんだけど。でも、運転しないんなら、どうやって出かけるの?」
「友達が迎えにきてくれるか、歩いてバス停まで行きます」
「それじゃ遊びに行くのも大変だ。ご飯は――寮の食堂だっけ」
財団の職員寮の食堂で、私の食事も作ってもらっている。
「買い物は通販ばかりです」
公邸周囲の検問は厳重だ。女中頭と護衛官といえども顔パスではない。トランクやエンジンルームはもちろん、全員いったん車から降りて身体検査され、バッグの中も調べられる。
2度の検問を通ると、外に出た、という感じがする。
「ひかるさん、さっきと今とで、メイクがぜんぜん違うよね、眉だけじゃなくて。案外おしゃれなんだね。私はこんなんよ」
見たところ、さっきと違うのは、チークとハイライトとマスカラだけだ。
「もとがきれいな人のほうが、おしゃれが苦手といいますから。
だからというわけではありませんが、私が『案外』おしゃれ、というのは心外です。警護のときの格好は野暮ったいでしょうか」
「フォーマルだからわかんなかった」
「あれはずいぶん工夫してあるんです。シャツのカフリンクスとか、カラーピンとか。よく見てください」
「ネクタイなんていつも紺の水玉模様じゃない」
「TVに映るときに多いだけです」
格式の高い場に出るときには、無難なものを選びがちになる。
「スタイルだって別人みたいだし」
「警護のときはシャツの下に、防刃防弾チョッキを着ていますので」
「それで野暮ったくなるのか! ひかるさん、そのチョッキをなんとかしなきゃ。もっと体に合うようにできないの?」
「あれでもだいぶよくなったんです。もともと柔軟性のない素材なんです。
橋本さんの――」
「美園! み・そ・の!」
「――美園さんのメイド服にも、いろいろご苦労があるかと思いますが」
「あれはね、いじっちゃいけないの。似合わない子は半年我慢。
もうすぐ衣更えか。ヘッドドレスのカチューシャはあんまり変えないでほしいのよ。いまのは前のよりよくとまるんだわ」
お側仕えのメイド服は、衣更えのたびに、ワンピース以外のところ(エプロン、ヘッドドレス、カラー、カフスなど)が新しいデザインに変わる。
「あの髪飾りは重そうですね」
金銀と玳瑁で薔薇をかたどった、女中頭のしるしだ。
「左右非対称に重量がかかるしね。油断してるとすぐずれる」
「女中頭が油断していると、すぐに人目につくわけですか。よくできていますね」
「そんなこと陸子さまが考えてたと思う?」
「では、美園さんの発明でしたか」
「うはっ、護衛官の毒舌がきたよ」
私はマスコミには『傲慢』『毒舌』で知られている。私は軽く受け流して、
「ワンピースが新しいデザインになるのは、いつでしょうね。私は前のパフスリーブのほうが好きでした」
メイド服のワンピースは、去年の冬から、夏冬ともにすっきりと肩の線を出すデザインになった。
「あれはね、評判悪かった。うちはスタイルに自信のある子が多いから。ああいうのって、自信のないとこを隠すにはいいんだけどさ。顔が大きいとか、肩がダメとか。
ま、うちの子の言うこときいてると、メイド服じゃなくなっちゃうけどね。肩出しにしろとか、ミニスカにしろとか。それじゃフレンチメイドだよ」
公邸のこと、陛下のこと、財団のこと。話すことはいくらでもあった。
ただ、平石緋沙子のことだけは、話題に出なかった。
夏休みが終わったばかりとはいえ、土曜日のディズニーランドは混んでいる。それでも、大物のアトラクションを2つ回るくらいはできた。
「ご飯食べて帰ろうか」
橋本美園は、腕時計を見てつぶやいた。昼食どきには、レストランの行列に並ぶ気になれず、空きっ腹を抱えてアトラクションを回っていた。
「ここで食べるんですか?」
「外で食べるの面倒くさい」
行列はもうはけていた。いつもの習慣で、私は先にレストランに入って、橋本美園を招き入れた。国王が女性の場合、護衛官は文字通りエスコート役を務める(『護衛』『警護』は英語ではescort)。
「ここだけレディ・ファーストじゃないの?」
アトラクションに入るときはすべて橋本美園を先に通していた。
「マナーでは、レストランだけ例外なんです」
何気なく答えてから、気づいて、複雑な気持ちになった。『レディ・ファースト』といっても、私も女だ。
「知らなかった。やっぱり私マナー弱いわ」
「メイドは、エスコートすることもされることもありませんからね」
「平石さんは、マナー強そうだな」
緊張が走った。
席に案内されるあいだに、頭を切り替えた。
「一緒にお仕事なさっていると、わかりますか」
「ローカルルールはいちいち瀬戸さんに質問して確かめてるって」
瀬戸さんは儀典担当のメイドだ。
公邸には、ヨーロッパや日本の一般的なマナーとは異なるローカルルールが多い。主に歴史上のいきがかりが原因だ。たとえばメイドが、職位にかかわらず全員同じ制服を着ているのも、公邸独特のものだろう。
「このあいだ彼女の私服姿を見ましたが、いいものを上手に着ていました。
黒づくめの格好で、手袋をはめていたんです。肘まで隠すようなのを。感動しました。私にはあんな格好はできません。暑すぎて」
「痩せ我慢が得意そうな顔してるもんね、平石さん」
「この時期のロンドンはもう涼しいでしょうから、そのつもりなのかもしれません」
「こっちでも、夜だけなら着られないこともないんじゃない?」
「私に着せたいんですか? では、今日のお礼に、オペラにでもお誘いしましょうか」
「ひかるさんはオペラなんて、警護でたくさん見てるでしょ」
「だからといって、夜の散歩では、ディズニーランドのお礼にはなりません」
と、私は話題を戻した。
「楽しい散歩だったみたいね?」
「そうですね。ずいぶん久しぶりでした。女の子に、好きだと言われたのは」
私は橋本美園の反応を楽しんだ。武術の達人のような、ゆったりとした鋭い視線で、私の表情を読んでいる。あの誇り高い、くもりのない顔をしている。
「……相手があの子でなければ、私もそんなことを言われてみたいものでございます」
言葉遣いが変わったことに、彼女自身は気づいているだろうか。
「そんなにお嫌いですか。私の目には、素直な子にしか見えません」
「私の懸念を申し上げましょう。
陸子さまはおそらく、あの子を使って、醜聞を作るおつもりです」